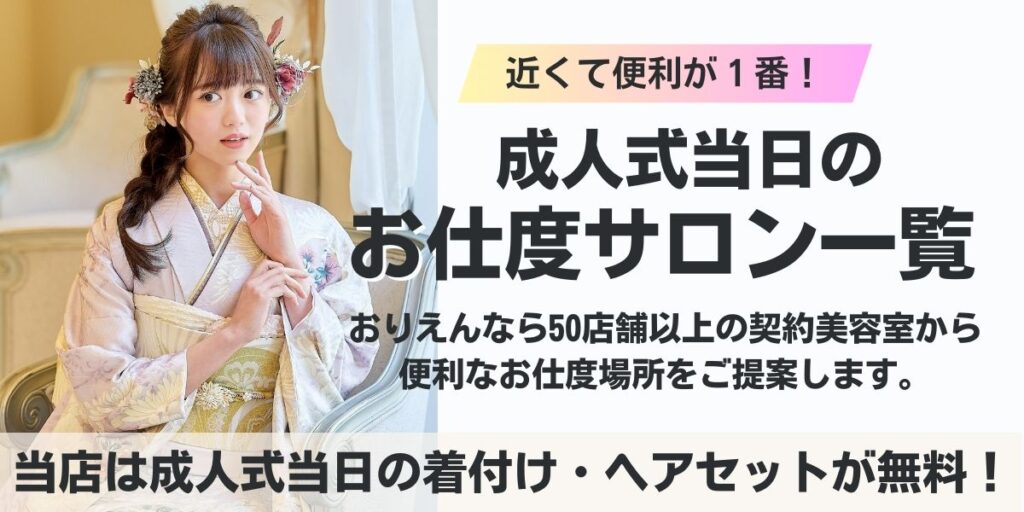FAQみんなの質問
成人式とは?由来・振袖との関係を歴史から紐解く
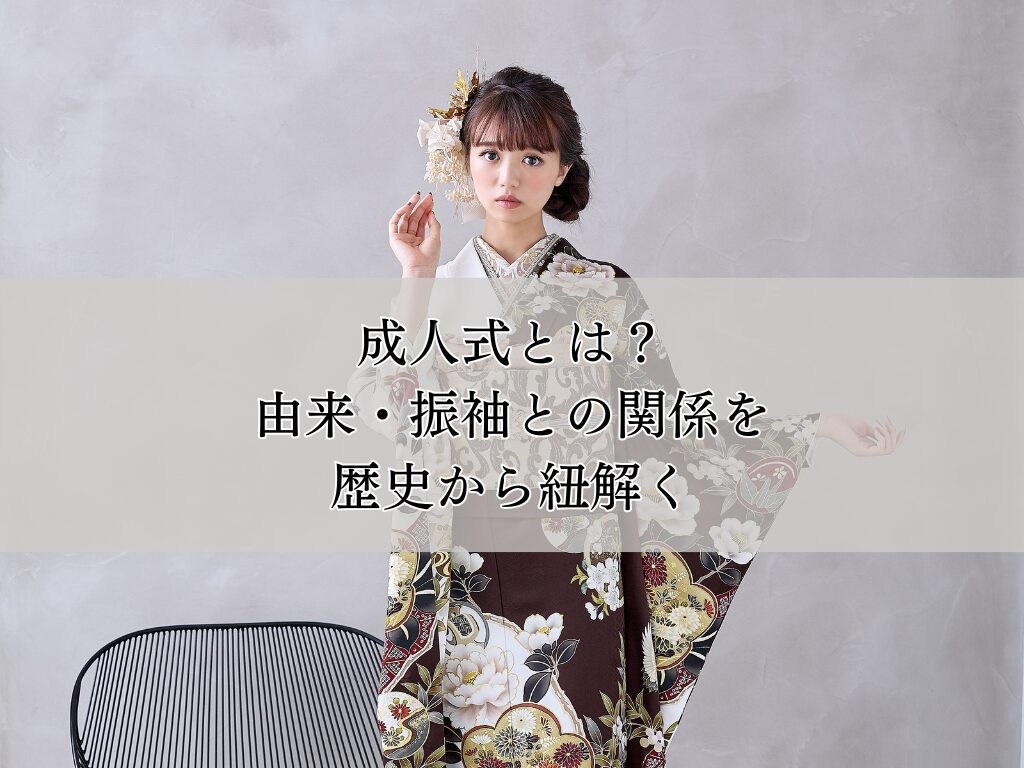
成人式。
華やかな振袖姿で写真に納まる姿は、多くの女性の憧れです。
しかし、その美しい衣装と伝統的な儀式には、長い歴史と深い意味が込められています。
今回は、成人式の由来と振袖との関わりを、歴史的背景から丁寧に紐解きながらご紹介します。
成人式で振袖を着る理由や、振袖の種類、選び方といった疑問も解消できるよう、分かりやすく解説します。
◆成人式の振袖の由来とは?歴史と進化
◇奈良時代からの「元服」と「裳着」
成人式の起源は、奈良時代以降に行われていた「元服」と「裳着」の儀式に遡ります。
元服は男子が、裳着は女子が、それぞれ数え年で12歳から16歳頃に執り行う通過儀礼でした。
元服では、髪型を大人の髪型に結い直し、幼名から成人にふさわしい新しい名前に改名するなど、外見と身分を大人へと変化させる儀式でした。
裳着では、女子が初めて裳(も)と呼ばれる、腰から下にまとう衣服を身に着けました。
髪を結い上げる髪上げも行われ、これらを通して子どもの象徴である髪型や衣服を大人のものへと改め、成長を祝うものでした。
これらの儀式は、単なる年齢の到達ではなく、社会の一員としての自覚を持つ重要な節目として位置づけられていました。
◇戦後の「青年祭」と成人の日の制定
現代の成人式の形が確立されたのは、戦後のことです。
昭和21年(1946年)、埼玉県蕨市で「青年祭」が開催されました。
これは、敗戦後の混乱と閉塞感の中で、未来を担う若者たちを励まし、社会への参加を促す目的で行われたものでした。
この青年祭の中で行われた「成年式」が、現在の成人式の原型となっています。
青年祭の様子は国や県にも注目され、昭和23年(1948年)には「成人の日」が国民の祝日として制定されました。
当初は1月15日でしたが、ハッピーマンデー制度の導入により、現在は1月の第2月曜日に変更されています。
◇現代の成人式 多様化する開催形態
現代の成人式は、地域や自治体によって開催時期や形態が様々です。
多くの地域では1月の第2月曜日に開催されますが、豪雪地帯などでは積雪の影響を考慮し、夏季に開催する地域もあります。
また、近年では、新成人の参加率向上のため、ゴールデンウィークやお盆休みなど、帰省しやすい時期に開催するケースも見られます。
さらに、ディズニーランドやシーワールドなど、地域の特徴を生かしたユニークな会場で開催される成人式も存在し、多様化が進んでいます。
企業によっては、社内成人式を開催するところもあり、企業文化や従業員の状況に応じて、多様な開催形態が見られるようになりました。

◆成人式と振袖の由来から深い繋がりを探る
◇振袖の起源と発展
振袖は、江戸時代に未婚の女性が正式な場で着るようになった着物です。
名前の由来はその長い袖が特徴で、肘から下が長く、「振る」ことができるほどです。
当初は袖丈が比較的短かったものが、時代を経るにつれて徐々に長くなっていきました。
袖丈が長くなった理由については諸説ありますが、舞踊など、身振り手振りを美しく見せるため、あるいは厄払いやお清めの意味合いがあったなどと言われています。
江戸時代後期には、振袖は未婚女性の第一礼装として確立されました。
◇振袖が成人式の正装になった理由
振袖が成人式の正装として定着した背景には、いくつかの理由が考えられます。
まず、振袖は未婚女性の第一礼装として最も格式が高い着物であることが挙げられます。
長い袖は、若さと清らかさを象徴し、晴れやかな門出にふさわしい装いとして選ばれました。
また、「振る」という動作には、厄払いやお清めといった意味合いもあり、新たな人生を始めるにあたり、身を清めるという意味も込められていたと考えられます。
さらに、日常生活では不便なほど長い袖は、特別な日だからこそ着用する装いであることを強調し、成人式という人生の節目における特別な意識を高める役割も果たしました。
◇成人式の由来と振袖の色柄と意味
振袖の色や柄にも、様々な意味が込められています。
赤や青、黒、白といった色は神聖な色とされ、桃色は恋の予感を、黄色は明るさや太陽を、緑は調和を、紫は高貴さを象徴するなど、色によって異なる意味合いを持っています。
柄についても、鶴は長寿、松竹梅は不屈の精神、亀甲紋は健康を願う象徴など、縁起の良いものが多く用いられます。
◆成人式の由来を理解する!振袖を選ぶための基礎知識
◇振袖の種類と特徴
振袖には、袖の長さによって大振袖、中振袖、小振袖の3種類があります。
大振袖は袖丈が最も長く(110cm前後)、最も格式が高い場で着用されます。
成人式や結婚式など、フォーマルな場面に適しています。
中振袖は袖丈が90cm程度で、セミフォーマルな場、例えば友人の結婚式二次会やパーティーなどに適しています。
小振袖は袖丈が75cmと最も短く、卒業式やカジュアルなパーティーなど、比較的カジュアルな場面に適しています。
◇自分に似合う振袖の選び方
自分に似合う振袖を選ぶためには、自分の体型や肌の色、そして好みに合った色柄を選ぶことが重要です。
体型に合わせて、すっきりとしたシルエットに見えるもの、肌の色に合う色、そして自分の好きなデザインを選ぶことで、より美しく着こなすことができます。
また、成人式当日の会場の雰囲気や、周りの人の服装なども考慮に入れて選ぶと良いでしょう。
事前に試着をして、実際に着てみてから決めることをおすすめします。

◆まとめ
今回は、成人式の由来と振袖との関わりについて、歴史的背景から丁寧に解説しました。
奈良時代からの「元服」と「裳着」の儀式、戦後の「青年祭」と成人の日の制定、そして現代の多様な成人式の開催形態についてご紹介しました。
成人式は、人生の大切な節目であり、振袖はその門出を彩る、伝統と美しさに満ちた衣装です。
この機会に、成人式と振袖の歴史と文化に触れてみてください。
そして、あなた自身の個性と魅力を最大限に引き出す、最高の振袖を選んで、忘れられない一日を過ごしてください。
堺市・和泉市周辺で振袖レンタル、購入するなら「おりえん」にお任せください!
おりえんには、日本中から集めた色とりどりの振袖がいっぱい!最新トレンドの帯・小物も充実しているから、お嬢様のなりたい振袖姿が叶います。
また、優しく丁寧なスタイリストが、あなたにぴったりの振袖コーディネートをお手伝いいたします。成人式を完全サポートするフルセット&特典も充実。
オトナになるあなたの大切な成人式を、もっと安心で、もっとかわいく。成人式をもっと特別にするお店、「振袖専門店おりえん」です。
振袖のことなら、レンタルや購入、ママ振りもお任せ!まずは気軽にお問合せください。
■ お電話の場合は 072-299-8037
■ 来店予約はこちら 来店予約フォーム
■ LINEでのご相談はこちら 公式LINEからお問合せ
■ 振袖カタログ請求はこちら カタログ請求フォーム
■ 全国対応!<送料無料>振袖ネットレンタルはこちら おりえんONLINEレンタル公式サイト
◇振袖コレクションを見る方はこちら 振袖コレクション
◇成人式当日のお仕度(無料)会場一覧はこちら 成人式お仕度会場一覧
◇お店のMAP・アクセスはこちら 店舗情報